皆さまこんにちは。前回はファイトケミカルと言われる成分の代表的なものを一覧でご紹介しました。今回はその食材と期待される効能をご紹介したいと思います。
ファイトケミカルと言えば何よりも抗酸化力を期待されて話題になっていますが、他にも高血圧低下やコレステロール値低下など食材によって嬉しい効能が期待されています。例えば赤ワインや茄子で知られるアントシアニンには血液サラサラ、老眼防止などの効能が期待されています。
植物中の成分は1万種類もあるとも言われていて、よく聞いたことのある成分だけが印象に残りがちですが実はもっとたくさんあるということです。
前回ご紹介した成分に、その効能を追記しましたので一覧で見て頂けたらと思います。
毎回同じような話をしますが、ファイトケミカルも食品成分表や食事摂取基準には記載がありません。まだ研究途上であること、分析方法が食材ごとに異なったりと指標を定めることがまだ難しく、必須栄養素とは定義されていません。
とはいえ研究が進み色々なことが分かってきていますので現段階では「第7の栄養素」とも「第8の栄養素」とも言われ注目を浴びています。植物のもつパワーに期待される効果や効能を信じていきたいと私も思うところです。
企業によっては分析値を商品に掲載しているものもありますので(例えばトマトのリコピンの量や豆腐に含まれるイソフラボンの量などがラベルに記載されている商品もある)、興味のある方はそういった点もチェックしてみるとよいかもしれません。
食材ごとのご紹介と併せてアメリカ国立がん研究所が1990年に発表された「フードピラミッド」というものをご紹介したいのですが、その前に必須栄養素とはまだ定義できない現段階での分析法を簡単にご紹介したいと思います。
先に結論をお伝えしますと、分析法がいくつもあり先ほどもお伝えしたように食材ごと(細かく言うと産地や季節、栽培法でも異なる)に調査をしてもメリットやデメリットがあり、結果の数字が全てではないということが分かります。目安として頂きたいこと、これからご紹介する「フードピラミッド」に掲載されている40種類の食材以外にも個性豊かな食材が数多くあること、そう思ってこちらの記事を読んで頂けると嬉しく思います。
目次
分析法は食材の特徴ごとに異なる
水溶性物質(ESR法、DPPH法、ORAC法)
✓ESR法
生体に関与する活性酸素(スーパーオキシド、ヒドロキシルラジカル、一重項酸素)をESR装置を使用して測定。より詳しく活性酸素消去活性の評価をしたい場合、具体的な特徴を得たい場合に用いられる
✓DPPH法
DPPH法は日本をはじめアジア圏で広く普及しているラジカル消去活性の測定方法。水溶性の植物に対し活性酸素を消去する力がどの野菜にどのくらいあるかを数字に表わしたもの。25,000検体以上のデータベースを作成しており、産地や品種の評価に活用されている。また加工品に使われる「酸化防止剤」がどの程度かを調べるのに用いられている
✓ORAC法
1992年にNIA(米国立老化研究所:National Institute on Aging)により開発、USDA(米農務省:United States Department of Agriculture)により改良されたラジカル消去活性の測定法
(欧米にて、食品の抗酸化力表示として使用されていた)
脂溶性物質 (SOAC法)
✓SOAC法
ビタミンEやカロテノイドなどの脂溶性成分を対象とした活性酸素消去活性の測定方法。トマトや人参、パプリカ、カボチャ、食用油などの評価に最適
※SOAC法はフード・アクション・ニッポンアワード2012にて、研究開発・新技術部門 最優秀賞を受賞した測定方法
測定法の欠点
このように抗酸化活性評価法は数多く存在し原理は明瞭であるが、実際の測定では注意すべきことがある。例えばDPPH法は、β‐カロテンやリコピンなど脂溶性成分はあまり抽出されない。
また強い抗酸化能のあるビタミンCは、50%エタノールではなく、5%メタリン酸溶液で抽出した方が良いという報告もある(ホウレンソウではメタリン酸抽出、タマネギではメタノール抽出が適しているなど)。
さらにもともと紫色をしている野菜などは、DPPH溶液の紫色と区別がつかないので紫色をみる方法では測定できない。
供試作物により抽出溶媒の検討が必要であり、適さない抽出溶媒を用いると栽培条件などによる変動が見過ごされることがあり、作物の抗酸化活性を担う物質は多様であるため溶媒による抽出には限界がある。
測定値は目安として活用
以上のことから分かるように、抗酸化能に寄与する成分は多岐にわたっており、種々の測定法も向き不向きがあるので、いくつかの方法で測定した方が良いということになります。
例えばDPPH法は栽培条件による影響など作物ごとの抗酸化活性変動を相対的に比較する場合に活用されたりしています。
前置きが長くなりましたがランキング付けすると分かり易い反面、誤解を生んでしまうこともあります。そのため「この40種類を食べておけば大丈夫!」ということではなく、あくまでも目安に、そしてファイトケミカルと言われるものは1万種類もあると言われており中には人間にとって悪さをするものや組み合わせや多量摂取で逆効果になることもあり、また個人差もあることからすべての人に当てはまるわけではありません。その上で、どんな食材にどんな効能が期待できるかを一覧で御覧頂けたらと思います。
アメリカ国立がん研究所「デザイナーフーズ計画」
デザイナーフーズ計画 (designer foods project) とは、アメリカ合衆国で実施された、植物に含まれる物質、すなわち、フィトケミカルの中で、がん予防の役立つ物質を含む食品を見い出し、がんの予防に役立てようとした計画である。
デザイナーフーズ計画は1990年代にアメリカ国立癌研究所 (NCI) によって、2000万ドルの予算を投じて、がんを予防するために、役に立つ可能性のあるフィトケミカルを特定し、それを加工食品に加える目的で開始された計画である。がんの予防に有効だと考えられる食品を公表した後、デザイナーフーズ計画は無くなった。
デザイナーフーズ計画では、がん予防に有効性があると考えられる野菜類が40種類ほど公開された。
以下の表は、公表された食品群である
デザイナーフーズ計画 – Wikipedia

前回の記事一覧より、抜粋して食材ごとの効能をご紹介
✓ポリフェノール類(水溶性)
✓フラボノイド系(色素)
アントシアニン(ナス、ブルーベリー、ブドウ、赤しそ)
目の網膜を酸化から守る、糖尿病を原因とした網膜症を予防、メタボリックシンドロームの発症予防、花粉症の改善効果、
冷え性改善、抗酸化作用、抗がん作用、抗菌作用、尿路感染症予防作用、認知症リスクを低下させる効果、
血液サラサラ(抗血栓効果)
カテキン(緑茶、果実類、カカオ)
抗菌作用、抗ウイルス作用
テアフラビン(紅茶やウーロン茶などの発酵茶)
血糖値上昇抑制、血中コレステロール値低下、感染症予防、殺菌作用、消炎作用
タンニン_カテキン、テアフラビンを総称して(お茶、レンコン)
抗酸化作用、抗がん作用、殺菌作用、消炎作用、抗ウイルス作用、血中コレステロール値低下、動脈硬化や高血圧、心臓疾患、
脳血管障害などの予防、脂肪を分解してエネルギーに変える働き(肥満予防)
ルチン(蕎麦)
ビタミンCの機能を助け毛細血管を強化、高血圧・血栓症・動脈硬化の予防、アレルギー発症予防、肌の老化予防、
風邪予防、抗がん作用
クエルチトリン(どくだみ茶)
利尿作用、便秘改善、血圧低下、抗動脈硬化作用、抗炎症作用
イソフラボン(大豆)
抗酸化作用、骨粗しょう症予防、悪玉コレステロール抑制
ノビレチン(シークワーサー)
抗アレルギー作用、血糖値上昇抑制、脂質代謝改善、肝機能障害の改善、抗がん作用、
記憶障害(認知症など)の改善、かゆみ・アレルギーの改善、メラニン合成阻害(美白)
フラバノン(柑橘類の果皮)
毛細血管を強くする作用、抗アレルギー作用、抗ウイルス作用
フラボン(セロリ、パセリ、ピーマン)
抗酸化作用、抗アレルギー作用
フラボノール(ブロッコリー、タマネギ、エシャロット)
主な成分:ケルセチン_ビタミンCの働きを助ける、血液サラサラ、動脈硬化予防、脳梗塞、心筋梗塞を予防、血中コレステロール値低下、関節痛の炎症を緩和、抗アレルギー作用
フラボノイド(タマネギ、レモン、バナナ)
抗酸化作用、デトックス作用、アンチエイジング、ストレス緩和、抗がん作用、免疫を整える、血液サラサラ
✓その他
クロロゲン酸(コーヒー)
ダイエット効果、アンチエイジング効果、糖尿病発症予防
エラグ酸(イチゴ、ラズベリー、クランベリー、ブドウ)
抗酸化作用、抗がん作用、糖尿病発症予防、抗炎症作用、アンチエイジング効果
リグナン(アカゴマ(亜麻仁)、ゴマ)
抗酸化作用、血中コレステロール低下、抗アレルギー作用、アルコール分解の促進、血圧低下、抗がん作用、肝機能の改善
セサミン(ゴマ)
抗酸化作用、血中コレステロール低下、抗炎症作用、酵素の働きをサポートし肝臓への負担を軽減、血圧低下、抗がん作用、肝機能の改善
クルクミン(ウコン)
免疫活性維持、抗酸化作用により免疫細胞のダメージを防ぐ、抗アレルギー作用、抗炎症作用、マクロファージや好中球による炎症を抑える
ルテオリン(ピーマン、大葉、春菊、パセリ、セロリ、エゴマ、ミント)
抗アレルギー作用、抗炎症作用、アレルギーに関わる酵素の作用を阻害し、抗炎症・抗アレルギー作用
ヘスペリチン(ゆず、すだち、温州ミカン、カボス)
抗アレルギー作用
ヒドロキシチロソール(オリーブ)
抗酸化作用、メタボリックシンドロームの発症予防・改善効果、美白効果
オレオカンタール(オリーブオイル)
抗酸化作用、抗炎症作用
オレウロペイン(オリーブオイル)
抗酸化作用、抗がん作用、免疫力アップ、アンチエイジング
レスベラトロール(赤ワイン)
抗酸化作用、老化防止、抗がん作用、糖尿病発症予防、血圧低下
アストラガリン(柿の葉)
抗酸化作用、抗アレルギー作用
✓カロテノイド類(脂溶性)
✓カロテン類(色素)
α-カロテン(ニンジン、カボチャ)
抗酸化力により遺伝子を守り、抗がん作用、免疫バリアを強化
β-カロテン(ニンジン、カボチャ、トマト)
ビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の免疫バリアを健康に保つ、抗がん作用、免疫バリア強化、抗酸化作用で動脈硬化を防ぐ
リコピン(トマト、スイカ)
抗炎症作用
✓キサントフィル類(色素)
ルテイン(ホウレンソウ、ブロッコリー、トウモロコシ)
白内障予防、眼疾患予防、ブルーライトによる網膜のダメージを軽減、美肌効果
ゼアキサンチン(カボチャ、トウモロコシ、モモ)
黄斑変性症を予防、白内障予防、ブルーライトによる網膜のダメージを軽減
カンタキサンチン(キノコ)
抗酸化作用、日光感受性から保護
フコキサンチン(ワカメやコンブ、ヒジキ、モズクなどの海藻類)
抗酸化作用、がん細胞の増殖を抑制、アポトーシス作用、肥満予防、糖尿病発症予防
アスタキサンチン(鮭、エビ、カニ)
眼精疲労改善、眼疾患予防、強力な抗酸化作用、動脈硬化予防、メタボリックシンドローム予防。筋肉疲労軽減、美白・美肌効果
β-クリプトキサンチン(ミカン、ホウレンソウ)
骨粗しょう症予防、糖尿病進行抑制、免疫力アップ、美肌効果
ルビキサンチン(ローズヒップ)
利尿作用、収れん作用、緩下作用、抗酸化作用、鎮静作用
✓モノテルペン(香気成分)
リモネン(レモン)
リラックス効果、覚醒効果、抗ガン作用、ダイエット効果、育毛・抜け毛予防、食欲増進
メントール(ハッカ)
鎮静効果、細胞の活性化、肌の引き締め効果、育毛効果、抗菌防臭
✓含硫化合物
イソチオシアネート系(ダイコン、ワサビ)
抗菌作用・抗がん作用、がん細胞のアポトーシスを誘導、肝臓の解毒酵素を増やし、有害物質を無毒化、血液サラサラ効果により、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞を予防
_スルフォラファン(ブロッコリー、ブロッコリースプラウト、キャベツ)
抗アレルギー作用(IgE産生を抑制)、抗菌作用、抗がん作用
システインスルホキシド系(玉ねぎ、キャベツ)
悪玉コレステロール低下
アリシン(ニンニク、玉ねぎ、ねぎ、ニラ)
攻撃力向上(NK細胞の活性化)、抗酸化力により遺伝子を守り、抗がん作用
ショウガオール(生姜:加熱)
抗アレルギー作用、抗炎症作用
✓多糖類
フコイダン(海藻類)
攻撃力向上(NK細胞の活性化)抗アレルギー作用、抗炎症作用
β-グルカン(キノコ)
攻撃力向上(NK細胞の活性化、樹状細胞を活性化して攻撃指令力を強化)
イヌリン(キクイモ、ゴボウ、玉ねぎ)
血糖値上昇抑制
サポニン(大豆)
肥満予防、コレステロール値低下、血流改善、免疫力アップ、肝機能を高める、咳や痰抑制
レンチナン(しいたけ)
攻撃力向上(NK細胞の活性化及び樹状細胞を活性化して攻撃指令力を強化)
グリフォラン(まいたけ)
攻撃力向上(T細胞とマクロファージを介して抗がん作用)
✓辛味成分
カプサイシン(唐辛子)
末梢血管の血流改善、冷え性改善、唾液や胃液の分泌を活発、食欲増進、 新陳代謝が活発、疲労解消
ジンゲロール(生姜:生)
攻撃力向上(免疫細胞の数を増やし、攻撃力を高める)抗アレルギー作用、抗炎症作用
✓芳香物化合物
シンナムアルデヒド(シナモン)
抗菌作用、風邪予防、消化促進効果、毛細血管の老化防止効果
コーヒー酸(コーヒー)
リラックス効果、脳の活性化、心臓病や脳卒中予防、大腸がんや肝がん予防、糖尿病の血糖値改善、脂肪燃焼促進による肥満防止
クマリン(桜の葉)
血液サラサラ
オイゲノール(バナナ)
攻撃力向上(白血球数を増やし、マクロファージを活性化)
食材を調理する時のポイント
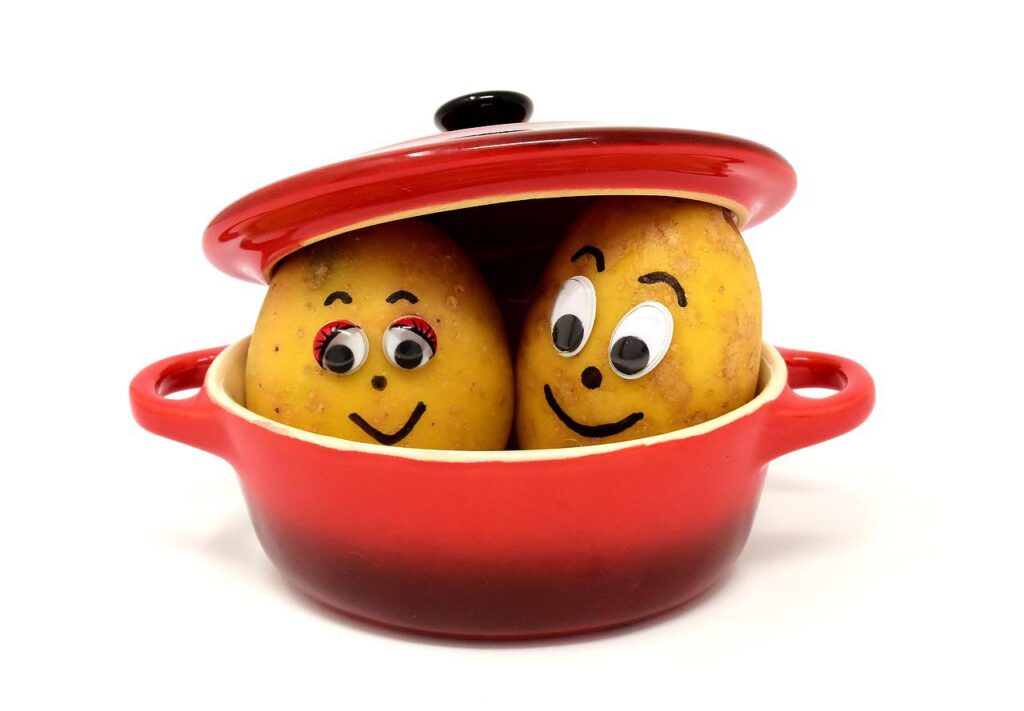
✓皮ごと食べましょう
外敵から身を守るため特に皮と実の間や種に多く含まれます。よく洗って皮ごと食べるのがお勧めです
✓傷あり野菜や無農薬野菜に成分が豊富
ファイトケミカルは外敵から身を守る成分のため、傷があったり紫外線や害虫などにさらされて生育している方が身を守るために増えます
✓食材の成分に合わせて調理法を選ぶ
水に溶ける、油に溶ける、熱に強い、弱いなど食材によって特徴があります。水溶性と脂溶性の食材を知り加熱するか生のままで食べるかを選んで調理すると効果的に栄養摂取できます
✓野菜の細胞壁を壊すイメージで加熱
ファイトケミカルは植物の細胞壁に保護された細胞膜や細胞内に含まれています。しかし細胞壁は包丁やミキサーで破砕する程度では壊れないため、サラダや生ジュースではファイトケミカルを効率的に摂取できません。熱を加えると細胞壁が壊れ、自然に細胞外に溶け出してきます。β-カロテンを含むニンジンの場合、そのまま搾った生ジュースよりもゆで汁の方が抗酸化力が100倍になるという実験データもあります。
さいごに
このように効能がそれぞれ異なり、健康を維持する上で積極的に摂り入れたい成分が詰まっています。
何よりも旬の食材はその時に栄養が最大限に蓄えられていますので、その時期に是非味わいたいと思います。
まだ研究途上のものもあり情報の更新が必要な場合はこちらに追記して参ります。
本日も最後までお付き合いくださいまして、有難うございました。