皆さまこんにちは。前回ビタミンCの必要性や効能などをご紹介しました。私たちになくてはならないビタミンCが何で体内で合成できないのでしょうか。合成できれば良いのにわざわざ欠落させる理由が進化を遂げる歴史上で何かがあったのでしょうね。色んな資料を読み、私なりの解釈ですがご紹介したいと思います。
目次
目次
多くの動物はビタミンCを体内で合成できる
実は多くの動物はビタミンCを体内で合成出来ると言われています。合成できないのはヒトをはじめ一部で、サル、ゾウ、モルモット、一部の鳥類などです。体内で合成できるため実際にはビタミンとは呼びません。
合成できる動物は何を原料としているのでしょうか。正解は「ブドウ糖(グルコース)」です。
皆さんの中で「ブドウ糖」と聞くと血糖値、糖尿病、糖質制限ダイエットなどのキーワードが連想されるのではないでしょうか。お米や小麦製品(パン、麺類)などの炭水化物に含まれる、「エネルギーの元となるもの」の大切な栄養成分です。もちろん摂り過ぎは良くないですがブドウ糖が無くては生きていけません。特に脳のエネルギー源はブドウ糖だからなのです。
動物もこのブドウ糖が重要なエネルギー源となるのですが、このブドウ糖からビタミンCを合成する経路を持っているのです。経路中のそれぞれの物質は4種類の酵素反応によって作られます。
ヒトは進化の過程で合成酵素を失ってしまった
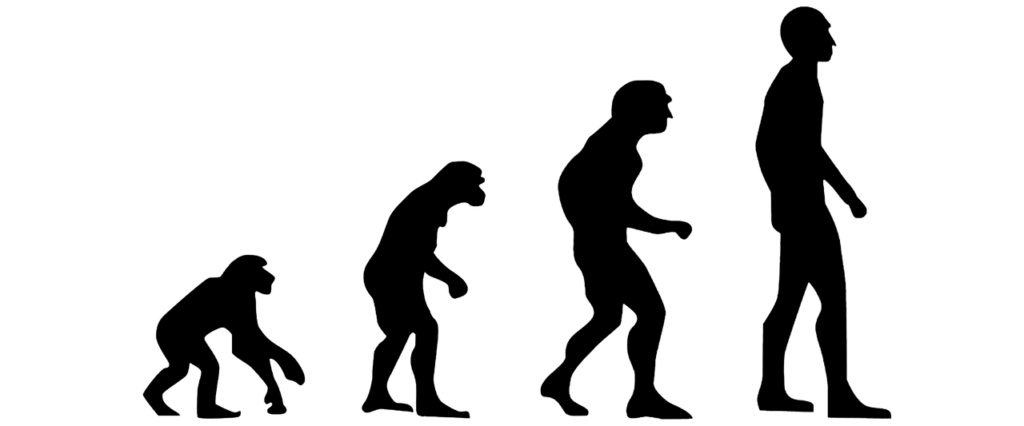
ヒトの先祖ははじめは合成酵素を持っていました。それが進化の中で変異して失っていったそうです。ではなぜヒトをはじめ一部の動物は合成する機能を失ってしまったのでしょうか。
合成する4つの酵素のうち、3つめまではヒトにも酵素は備わっています。しかし最終反応である最後の一つの酵素だけが欠損してしまったために体内で合成できなくなってしまったと言われています。理由は定かになっていません。長い歴史の進化の中でこの酵素の遺伝子に変異が起こり欠損してしまったと考えられています。
1果物などを日常的に補給できる能力と環境があったから
考えられることは果物をエサにするようなサル、ゾウ、一部の鳥類などを含めヒトは外部からビタミンCを日常的に補給できる能力も環境もあったため、合成機能を失っても良いと歴史の進化の中で機能的に判断されていったのかもしれません。
2尿酸がビタミンCの機能の一部を代用できる可能性があったから
歴史上の進化の途中において、ヒトは「尿酸」を分解する酵素も欠損しています。尿酸と言えば痛風を思い出す方も多いと思いますが、尿酸はビタミンCよりもはるかに強力な抗酸化物質として働いているのです。体内に一定量存在することには大きな意義があり、活性酸素と尿酸は互いを打ち消しあう作用を持っていて、どちらかが多すぎても少なすぎても酸化ストレスや炎症をきたすことが示唆されています。霊長類では少なくとも尿酸がビタミンCの機能の一部を引き継いでいる可能性があり、能力の喪失と関連している可能性があるとしています。
3脳を守るため説
またビタミンC研究の第一人者であるライナスポーリング博士は著書の中でこのように話しています。
「人類がビタミンC合成能を失ったのは、脳を守るためだ」
ではなぜ脳を守ることがビタミンC合成を失ったことに繋がるのでしょう。実はビタミンCとブドウ糖の化学式がとても似ているのです。このブドウ糖の摂取により4つの酵素でビタミンCを合成しているのですが、脳重量が重いヒトにとってはブドウ糖の必要性も増します。そこで脳を守るためにブドウ糖を充分に脳で活かせるようあえて合成機能を欠損させたのではないかと言われています。
ちなみに牛乳にはビタミンCはほとんど含まれていません。ブドウ糖とタンパク質があれば子牛が自分で合成できるためです。またヨーグルトは乳酸発酵して作られますが、乳酸菌が発酵過程においてビタミンCを生成します。そのためヨーグルトにはビタミンCが微量に含まれることがあります。
また肉食動物は草食動物を食べますが、タンパク質が消化酵素で分解されて生成されたアミノ酸からブドウ糖を作れるのです。
さいごに|歴史上の進化で淘汰された自然の恵みを頂く大切さを知る
栄養療法の世界的権威であるジョナサンライト医師の名言(と私は勝手に思っています)をご紹介します。
「血液中のビタミンC欠乏は、人類全体に共通した遺伝的障害である」
微生物はブドウ糖だけあれば生きていけます。しかしヒトは様々な栄養素を必要とし、ビタミンに至っては13種類もの成分を補給し続けないと生きていけません。様々な生命体は歴史の中で進化を繰り返し、必要な栄養素を頂きながら私たちは生かされています。
栄養学はそれぞれの成分の特徴、必要性、欠乏症や過剰症、どのような食材にどんな栄養素がどのくらい含まれているかを勉強します。組み合わせにより吸収率が上がることや逆に阻害されてしまうことなどの組み合わせも知り、さらに調理法によっても吸収が良くなったり失われてしまったり総合的に学んだ上で予算や保存なども考えながら献立を作成していき、料理として私たちは食事を頂きます。
しかし仕事として作業していた時はこのように奥深くまで考えていませんでした。きっと学生の時に授業で触れていたのでしょうが、身についていませんでした。実際に仕事上では栄養価計算ソフトに食材ごとの栄養価と原価を登録すればレシピの組み合わせでいくらでも簡単に栄養価計算できます。そのため何も考えずただの作業になっていました。仕事外でも同じです。食事は日常のことで時に面倒に感じたり体調が優れず準備が大変な時もあります。
しかし改めて、自然の歴史の中で繰り返されてきた生命体には様々な条件下で淘汰されて今があることを知ることができます。それはサプリにも完全栄養食と言われるような加工品にも真似することの出来ない自然のパワーが備わっているように感じます。なるべく加工品に頼ることなく、自然の恵みに感謝しながら、身近な食材を大切にして頂きたいと思います。
本日も最後までお付き合いくださいまして、有難うございました。
