皆さまこんにちは。佐々木漬物の御主人が青年の頃に発表した資料から、御主人の原点を知ることができました。
農業と経営に真剣に向き合った時に気が付いた、「なんで米ぬかに埋まっている畑の野菜はいつまで経っても元気なんだろう?」という疑問からぬか漬けが人間の身体にも良いということを経験から知り、こだわりの発酵ぬか漬けを作るために独学で知識と技術を身に付けていきました。
現代では「健康的な生活を支える三原則は、快食、快眠、快便」と言われています。
本日も佐々木漬物のこだわりの一つ、「酪酸菌」にまつわるお話をしたいと思います。
目次
目次
糖質は単糖からなり、二糖、オリゴ糖、多糖と結合する数が異なる
代表的なものをご紹介いたします。
<単糖類>グルコース、ガラクトース、フルクトース、マンノース
<二糖類>マルトース(グルコース+グルコース) 麦芽糖
スクロース(グルコース+フルクトース) ショ糖
ラクトース(ガラクトース+グルコース) 乳糖
<三糖類>マルトトリオース、シクロデキストリン、ラフィノース
<四糖類>スタキオース
<多糖類>非常に多くの担当(数千から数百万分子)が結合してできたもの
✓ホモ多糖(でんぷん、デキストリン、グリコーゲン、セルロース)
✓ヘテロ多糖(ヘパリン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、ペクチン、キチン)
オリゴ糖とは
グルコースやフルクトースなどの単糖類がグリコシド結合によって3個~数個結合した糖類を言います。
単糖からの説明で言うと、<三糖類>、<四糖類>がオリゴ糖ということです。
オリゴ糖の「オリゴ」はギリシャ語で「少ない」という意味で、「少糖類」と呼ぶこともあります。
オリゴ糖を多く含む食材
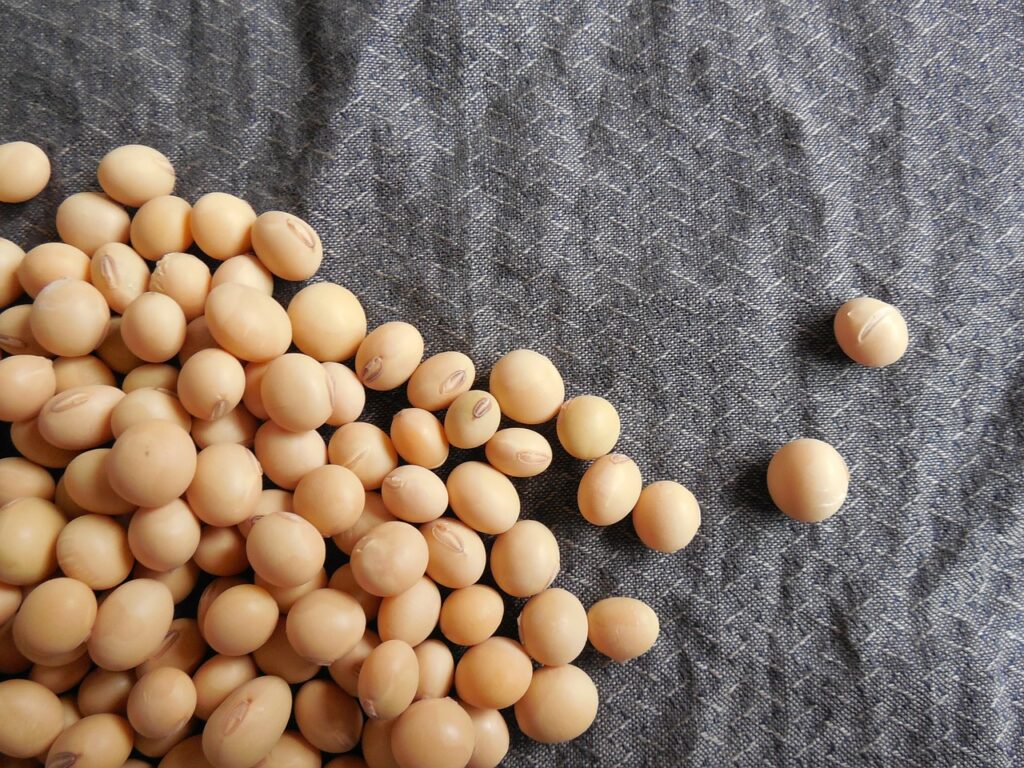
オリゴ糖は胃で消化・吸収されにくいため、そのまま大腸まで届きます。
食物繊維と同様に、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌のエサとなり、腸内環境が整います。
糖質のうち、最小単位である単糖が2個から10個程度結びついたもので、少糖とも言う。
低消化性(低エネルギー)で、整腸作用や腸内細菌を増やす作用などが知られている。単糖が2個から10個程度結びついたもので、少糖類とも言われています。
ただし明確な定義はなく、ショ糖・麦芽糖・乳糖などの二糖類も本来はオリゴ糖の仲間といえますが、一般的には3つ以上の糖が結びついたものをオリゴ糖と呼んでいる場合が多いようです。砂糖を原料に酵素を作用させて作られるフラクトオリゴ糖や、大豆から天然成分を抽出・分離させた大豆オリゴ糖、乳糖にβ-ガラクトシダーゼを作用させたガラクトオリゴ糖などが代表的です。ビフィズス菌などの善玉菌と呼ばれる腸内細菌の栄養源となってそれらを増やす効果があり、特定保健用食品として認められています。またトレハロース・パラチノースは、むし歯になりにくいことや消化されにくくエネルギーとして使われにくいことから、代替甘味料としてよく使われています。
オリゴ糖 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
オリゴ糖を多く含む食品として一例ですがご紹介いたします。
<果物>バナナ リンゴ キウイフルーツ
<豆類>大豆 枝豆 /(大豆加工品)きな粉 豆腐 味噌 醤油
<野菜類>ごぼう 玉ねぎ 長ねぎ にんにく エシャロット キャベツ アスパラガス ブロッコリー カリフラワー アボカド
<その他>じゃがいも ヤーコン とうもろこし さとうきび 甜菜 牛乳 ヨーグルト ハチミツ
母乳にオリゴ糖が含まれている理由とは?
ヒトはオリゴ糖を分解する消化酵素を持っていません。
それなのに何で母乳にオリゴ糖が含まれているのでしょう?
その理由は、乳児の腸内フローラを育成させるためなのです。
以前ご紹介した「短鎖脂肪酸」を生成させ、腸内の悪玉菌の増殖を抑制する環境を形成させるためと言われています。
胎内にいる時は無菌状態と言われています。そして出生時の産道の状態や出生後の母乳などで母親から皮膚の常在菌や腸内細菌が引き継がれます。
そして1週間ほどもすればビフィズス菌が大半を占めるようになるのですが、同時に悪玉菌や日和見菌も受け継いでいるという訳です。
その後離乳食も始まり外的環境にも触れることで赤ちゃんの腸内環境が徐々に多様性を見せ、3歳頃までに成人と同じような腸内環境に落ち着くと言われています。
腸内環境は持って生まれた個人差があるが、変えることができる
このように一般的には3歳頃までに人それぞれの腸内環境が整うのですが、その後一生メンバー構成が変わらない、ということではありません。
自分で選んで摂り入れる食べ物や生活環境でこの腸内環境を決めることができます。
それが発酵食品と、前回の記事で紹介した食物繊維や今回のお話のオリゴ糖などです。
乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などの善玉菌を腸内で育成させることで腸内環境を整えることができるのです。
人間にとって有益な作用をもたらしてくれる菌を善玉菌、腐敗や食中毒の原因菌を悪玉菌と呼び分けていて、さらにそのどちらでもない中間菌も存在します。
善玉菌:悪玉菌:中間菌=2:1:7が理想と言われています。
このバランスが生活環境や普段の食生活により、善玉菌優位か悪玉菌優位かに変化するのです。
どちらでもない中間菌のことを「日和見菌」とも言うのですが、善玉菌優位の時はこの中間菌も善玉優勢に、また悪玉菌優位の時は中間菌は悪玉優勢に変化するのです。そのため「日和見菌」と呼ばれているのです。
この細菌たちはエサがあると増えるのです。善玉菌が好きなエサと、悪玉菌が好きなエサ、それぞれ好みが分かれているのです。
善玉菌優位の腸内環境を維持するために乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などを食べ物から補充し、さらに善玉菌の好きなエサを摂取することが大切です。
発酵食文化日本

発酵食品として漬物や味噌、醤油、お酢、甘酒、納豆などを食べて善玉菌をコツコツと継続して摂取できていたことが考えられます。
特に漬物や味噌は地域の特性がよく表れ、「お国自慢」とも言える様々な漬物や味噌が出回っています。
発酵食文化の発展と共に日本人の腸内環境は善玉菌を摂り入れてきた民族と言えるでしょう。
さらにぬか漬けにしか存在しない酪酸菌。江戸時代までは日本人は米を玄米のままで食べていました。
江戸時代に入ると上流階級の方々が精米して白米を食べるようになりました。
そして徐々に一般庶民にも広がっていくのですが、同時に米ぬかという廃棄物が発生することになるのです。
この米ぬかが経験から栄養が豊富ということを知り、ぬか漬けにしたり魚にまぶして保存性を高めたり、家畜の飼料や畑の肥料として有効活用してきたのです。
こうして米食文化である日本人は酪酸菌も獲得し、乳酸菌やビフィズス菌がより住みやすい腸内環境に整えてきていたのです。
さいごに|大豆は”世界五大健康食品”のひとつです
オリゴ糖を多く含む大豆。上記にご紹介したように加工品もたくさんあります。
”世界五大健康食品”って聞いたことありますでしょうか?
15年以上前になりますが、アメリカの健康専門月間誌によると、韓国のキムチをはじめ、日本の大豆、スペインのオリーブオイル、ギリシャのヨーグルト、インドのレンズ豆の5品目が選出されたと報じられました。
アメリカの健康専門月間誌「health」
健康:信頼できる共感的な健康とウェルネス情報 (health.com)
日本人の昔の食生活から考えると、身近な食材が腸内細菌を育んできたと言えるでしょう。
先代の知恵にあやかり、日本の和食文化、伝統文化を大切にしていきたいと改めて感じています。
