皆さまこんにちは。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
前回の記事で3か月間の振り返りをし、そして今年はこれからやる業務を一つずつ形にしていきたいと思っているとお話しました。この3か月間で行っていたことは以下の内容です。
✓民間会社を通して利用者さんのお宅へ訪問し、①朝食の準備②買い物代行、現在の体調を確認しながら普段食べているものの把握とアドバイス、料理作り、掃除、話し相手、外出同行など③3日分の食事の作り置き④その他スポット対応
✓地域でのボランティア活動への参加①認知症カフェへの参加②スタッフの方との交流③地域活動への参加
✓規格外野菜販売のボランティア活動
✓その他記事執筆(趣味の領域で)ほか
その中で私は特に療養中の在宅患者さんに向けた治療食のサポートをサービスとしてやっていきたいというのがひとつあります。そう思ったいきさつは以前働いていた栄養士職において、病院や高齢者施設で給食を提供していた時に感じていたことです。治療食を召し上がっていた患者さんはご自宅へ退院されたあと、どうやってこの食事を続けていくのか、老健から在宅復帰できた利用者さんはご自宅でこの刻み食を工夫していけるのか…。本職の栄養士でも治療食献立には知識と技術が必要なものなのに、在宅療養になる方のその後がいつも気になっていました。2025年問題へ向けて在宅医療が増えている中で制度や専門的な資格が整いつつあるものの、実際にどの程度寄り添えてご本人やご家族にサポートできているのか、実際に在宅訪問栄養士の方が割合としてどの位ご活躍されているのか私には実態がわかっていなく勉強不足だと感じていると前回の記事でもお話しました。
私が今やっている仕事は栄養士職とは関係なく在宅療養されているお客さんのところに訪問して食事作りをしたりしていますが、そもそも介護保険や診療報酬で出来るサービスがあるなら私が行かなくても保険内で利用者さんはサービスを受けられるのではないのかとずっと疑問に思っていたのです。
実際に腎臓を患って退院した利用者さんは、月1回外来にかかっていますがご自宅での食事作りの資料を見ても正直よくわからないと仰っておりました。ここにサポートしてもらえるご家族や親戚がいたらまた違うのかもしれませんが、おひとりで暮らしてカリウム制限と塩分制限を守りつつ、エネルギーとタンパク質の一日の摂取量をコントロールするというのは難しいのではと感じています。
そんな方に栄養面で寄り添っていけるサービスは実際に確立されています。まだまだ勉強中の身ではありますが、現状を少しだけまとめましたのでご紹介したいと思います。
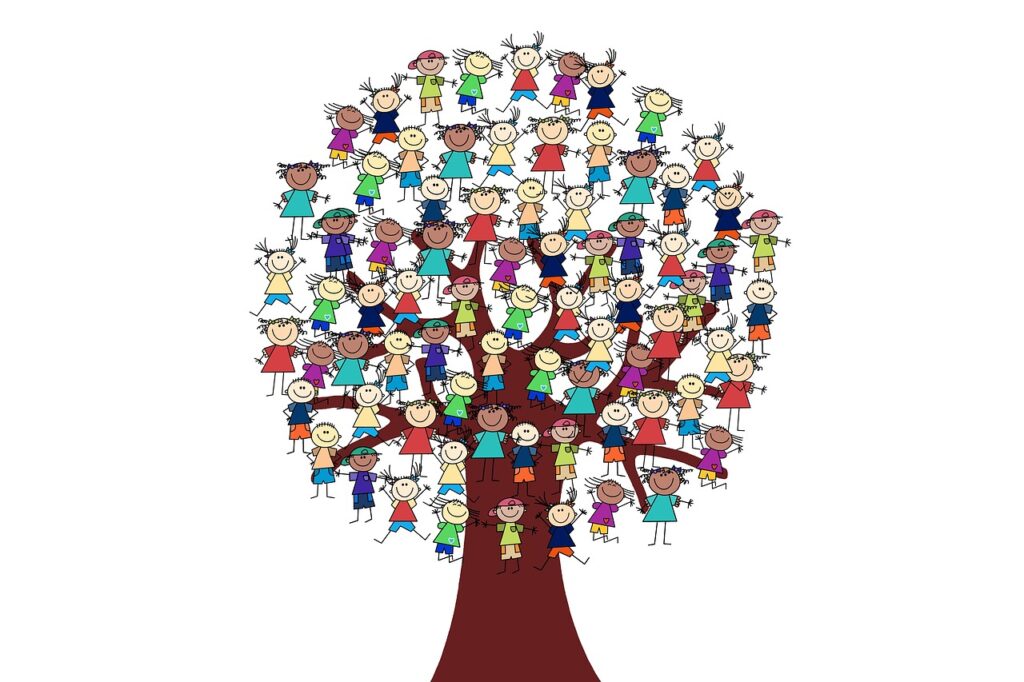
目次
目次
栄養ケア・ステーションとは
栄養ケア・ステーション(栄養CS)とは栄養ケアを提供する地域密着型の拠点。地域の皆さまの食の課題に、全国の管理栄養士・栄養士が対応します(日本栄養士会が統括し、各県の栄養士会がまとめています)。
全国の栄養ケア・ステーションと認定栄養ケア・ステーション
2021年4月1日現在 356拠点
登録管理栄養士・栄養士4,973名
栄養ケア・ステーション
公益社団法人 日本栄養士会 (dietitian.or.jp)
✓業務内容(一例)
現在全国にあり、業務内容は診療報酬、介護報酬にかかわる栄養相談や特定保健指導、そして通いの場やサロンでの活動が主なもの。管理栄養士が身近で気軽に相談できる存在として、地域の医療機関・介護施設・自治体・保健センターなどと連携し幅広く手厚いサポート。例えば薬局内でも処方箋を持っていない方でも利用できる
✓認定栄養ケア・ステーションの業務・・・派遣による栄養指導等
①栄養相談
クリニックや歯科と連携した疾病に関する食事療法や、疾患をお持ちでない方の健康づくりのご相談
②訪問栄養相談
通院が困難な在宅療養中の方に対し、ご自宅での栄養相談
✓イベントの栄養相談や講演会等の講師派遣
①健康イベント・セミナー
地域の企業や自治体・学校等の「食事や栄養に関するセミナー」や「研修会」へ講師の派遣、イベントの企画・運営のサポート
②料理教室、栄養教室
地域の企業や自治体・学校等の「料理教室」や「栄養教室」の企画・運営のサポート
✓診療報酬点数
医療機関在籍の管理栄養士「外来栄養食事指導料1」で算定 初回260点 2回目以降対面で200点
診療所以外の管理栄養士「外来栄養食事指導料2」 で算定 初回250点 2回目以降190点 (←新設)
または「在宅患者訪問栄養食事指導料2」で算定 単一建物患者が一名の場合 初回510点
平成30年度改定時と令和2年度診療報酬改定で、都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションにおいて、外来、在宅患者訪問栄養食事指導料が算定できるようになりました。
診療報酬点数上では「外来栄養食事指導料2」として、院内に管理栄養士がいないクリニックでも外部の管理栄養士の支援を受けつつ栄養指導を行うことに対し診療報酬上の評価がついてきたということです。
「認定栄養ケア・ステーション」の認定を受けるために
栄養士会に入会していることを前提に、生涯教育を受けていることなど条件があり日本栄養士会に申請をして認定を受ける流れとなります。
都道府県栄養士会へ申請(申請書、添付書類6種、研修、その他)→面談→受理→内容精査→受理、日本栄養士会へ申請→審査(認定審査会、年2回)→審査(認定委員会、年2回)→理事会→承認→都道府県栄養士会経由で認定通知
※3年ごと更新
公益社団法人 日本栄養士会 栄養ケア・ステーション認定制度規則
(改正 2021 年 9 月 11 日) kisoku.pdf (dietitian.or.jp)
公益社団法人日本栄養士会 栄養ケア・ステーション認定制度規則施行細則
(改正 2021 年 10 月 1 日) saisoku.pdf (dietitian.or.jp)
✓申請に要する手数料(規則第 33条第 1 項)
申請手数料11,000 円
審査手数料22,000 円
認定手数料11,000 円
✓認定の更新に要する手数料(規則第 33 条第 2 項)
更新申請手数料5,500 円
更新審査手数料11,000 円
更新認定手数料5,500 円
実際にどの程度活動が広がっているのでしょうか。栄養ケア・ステーションの背景と発展と拠点の広がりを時系列で見てみるとこのようになります。
2006年全都道府県栄養士会への設置
2008年特定検診・特定保健指導を事業の中心とする
2010年栄養ケア・ステーション設定、商標登録
2012年47拠点
2018年栄養ケア・ステーション、認定制度設立
2020年時点 拠点344まで増える。380箇所まで拡げることを目標としていたが、2021年時点で356拠点にとどまる。
実際の配置状況と現在の課題

では実態としてはどうなのでしょう。厚生労働省が紹介しているこちらの公開資料を拝見いたしました。実務ベースでご紹介されていて、とてもリアルな現実と課題に皆さんが向き合っている様子が大変よく分かります。資料から一部だけ抜粋させて頂きました。
第139回 市町村職員を対象とするセミナー H30.10.16(火)厚生労働省講堂
地域包括ケアシステムの推進における 行政管理栄養士等の関与に関する 実態調査~市町村結果について~ (mhlw.go.jp)
兵庫県伊丹健康福祉事務所
地域包括ケアシステム構築における“行政栄養士の役割”とは (平成28~29年度 地域保健総合推進事業)
① 管理栄養士の配置状況
行政の中でも特に高齢者部門の配置状況が低い傾向にある
介護・高齢者部門の管理栄養士等配置状況 99(10.4%)
地域包括支援センターの管理栄養士等配置状況
2,710センターのうち 48(1.8%)であることがわかった
地域ケア会議を開催している798市区町村のうち、参加しているのは217(27.2%)
<参加していない理由>
○ 最も多い「栄養士を充分に活用できていない」、次いで「栄養改善が課題として認識されていない」
○ その他「個別検討で栄養指導がメインとなる事例がない」、「マンパワー不足」、「他職種で対応している」、「必要に応じて 参加できる体制ではある」など
在宅医療・介護連携会議を開催している591市区町村のうち、参加しているのは136(23.0%)
○ 最も多い「栄養士を充分に活用できていない」次いで「栄養改善が課題として認識されていない」
○ その他、「栄養士が配置されていない」、 「介護予防事業に栄養士が関与していないため」、「医療と介護の連携が検討の主題であるため」、「入退院時に関与していないため」など
② 関連事業への管理栄養士等の関与状況、意識
地域包括ケアシステムの推進に関する活動について
必要と思い関わっている市町村栄養士は190(19.9%)、606(63.4%)は必要と思うが関わることができていなかった
一方、37(3.9%)は必要と思わないと回答
市町村管理栄養士として取り組みたいことは、多職種連携、低栄養予防対策、訪問を含め個別栄養指導、介護・高齢部門への管理栄養士の配置促進の順であった。
③ 保健所や保健所管理栄養士等への期待
保健所や保健所管理栄養士に対する要望は情報発信に関するものが最も多く、リーダーシップ、人材育成、組織体制整備なども記載
考察1:行政管理栄養士の関与
地域ケア会議や在宅医療・介護連携会議等における管理栄養士の関与は少なく、多くの市町村管理栄養士が地域包括ケアシステムの推進に関わることができていない
<関与できていない理由>
● 担当部門の管理栄養士配置率低い ● 地域の管理栄養士の育成確保不足 ● 栄養・食生活改善が課題として認識されていない
考察2:市町村管理栄養士の役割
市町村管理栄養士の具体的な取組
● 介護予防や生活習慣病重症化予防等における個別対応(栄養アセスメン ト、栄養相談、訪問栄養食事指導) ● 栄養改善教室のプログラム企画 ● 食環境整備 ⇒ 配食事業者への介入、共食の推進 ● ボランティア養成(食生活改善推進員、介護サポーター)
考察3:保健所管理栄養士の役割
【市町村からの期待】● 具体的ノウハウなどの情報発信 ● リーダーシップ ● 人材育成 ● 組織体制整備● 高齢者の栄養・食生活実態把握 ● 社会資源の把握 ● 栄養士の連携強化 ● 関係職種への理解促進を図る
地域ネットワーク構築に向けてのグループワーク
≪現状と課題≫
・市町庁内にて“健康増進部門”と“介護保険部門”が連携できていない
・自立支援型個別地域ケア会議への管理栄養士の参画状況には地域差有り。 行政栄養士だけで参加するのは業務量的に負担。栄養士会に協力を求めたい
・訪問栄養食事指導のニーズもある。指導ツールを統一したい。栄養士会に協力を求めたい
・地域の同職種栄養士(病院、施設、地活等)の連携の場づくりには行政栄養士(特に県保健所)の積極的な介入が必要。多職種連携を進める上でも同様
・各地域で取組をしている人はいるが点々としている。点をどう線につなげるか。現場から上がった声を拾い上げ、サポートすることも大切
抜粋しておりますのでこちらだけを読むと偏りが出てしまいます。実際の資料にも目を通して頂けると嬉しいところですが、ポイントとして個人的に感じたことは、私は民間企業で栄養士職に従事していましたが、ニーズに対して行政も民間も関係なくマンパワー不足といった意味では同じなんだなぁという感想でした。需要と供給が見合っていないこと、またその予算が取れていないため必要な人員を確保できないでいることが見受けられます。実績が伴わないと増員の予算を入れて頂けないと言った方が正解でしょうか。官民問わず実績を積み上げていくしかないかもしれません。
しかし令和2年度において診療報酬の対象になったことが、これからの変化に期待したいところであります。
私のいる街での設置状況
私のいる千葉県内はどうかと言いますと、14か所(日本全国の4%)、6つの市に設置されています(佐倉市、八街市、千葉市(若葉区、稲毛区、緑区)、旭市、松戸市2か所、柏市6か所)。
その事業は公益社団法人千葉県栄養士会をはじめ、大手薬局、訪問看護ステーション、NPO法人、個人での設立と様々な拠点を窓口とされてご活躍されています。
私が仕事として訪問しているお客さんの街にはこの栄養ケア・ステーションはありませんが、民間企業が近隣の地域包括支援センターと連携を図っているため、そこからご相談が入るようになっています。「こんなことで困っている利用者さんがいるんだけど介護保険では出来ない、そちらの方で様子を見てもらえないか」といった流れのようです。介護保険で出来ることと出来ないことの連携を知り、とても良いサービスだとこちらの会社を知った時、いちばん初めにそう感じました。そしてこれが栄養面でもうまく連携が図れるといいなぁと切実に思いました(実際はきちんと連携が取れてうまくいっている地域ももちろんあると思いますが)。せっかくこれまで築き上げてこられた方々の活動や実績が認められて診療報酬の算定に新設されたり新たな制度が出来ているので、もっと広く知って頂きより地域住民の方々に寄り添えるような場になっていけると私も嬉しく思います。
しかし私は実際には栄養ケア・ステーションをまだ見かけたことがありません。薬局内での管理栄養士は増えた感覚はありますのでもっと身近な存在であってほしいと思います。大切なことは身近にあること、気軽に関われること。ちょっと知りたいだけなんだけどレスポンスが悪い、いちいち手続きが必要、毎回一から同じことを話さなくてはいけない…そういった不便なものでなく、とにかく気軽に関われる存在が身近にあることも、世の中の仕組みのひとつとして必要ではないかのかなと感じています。
さいごに
2025年問題と言われている高齢化社会が目前に迫っております。そして今現在も、実際にニーズがあるものの活かしきれていない、マンパワーが足りていない、サービス提供とマッチしない、タイミングが合わないなどの理由で困っている利用者さんと繋がらないというケースがあるようにも感じていました。
介護保険で出来ないサービスを民間が行っています。医療も自費で行うサービスもあります。官民で高齢者を支えている現在の世の中に、管理栄養士としてできるサービスも自費でできる仕組みづくりを実際に始めている個人や団体もいますので、そういったところで私も活動していけるよう出来ることから始めていきたいと思います。
課題はたくさんあります。勉強、調査、情報、準備、どれもまだまだと思うことがあり随分先のような感覚に陥ってしまっていますが、でも一番は自分のやる気次第だと頭では分かっています。まずひとつ形にできるよう進んでみて、こちらでまた良いご報告が出来るようにしたいです。最後までお付き合いくださいまして、有難う御座いました。
